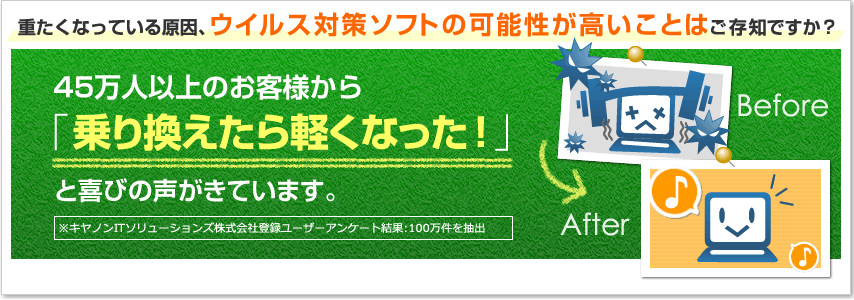人前であがってしまう理由(と、それを克服する方法)/ミカエル・チョウ
人前であがってしまう理由を脳科学的な角度から解説し、その対処法を教えてくれています。
(所要時間:約5分)
動画の内容 (全文書き起こし)
手のひらが汗ばみ、鼓動がはやり、胃が締めつけられる。助けを求めることはできません。息ができないくらい のどが苦しいだけでなく、そんなことをしたら恥ずかしいのですから。いいえ 怪物に狙われているわけではありません。人前で話しているのです。
死んだ方がましだと思う人もいるかもしれませんね。死んでしまえば、何も感じることはありませんが、演壇の上ではあがってしまうのですから。
でも、誰もが人生のどこかで、人前で話さなければならないので、克服しなければなりません。まず、「人前であがる」ということがどういうことかを理解しましょう。
人は社会的な動物で、人からの評価が気になるものです。人前で話すことで評価が左右されるかもしれません。話し始める前にこう思うでしょう。「最低で馬鹿だと思われたらどうしよう?」
「馬鹿だと思われたくない」というこの恐れは、コントロールしにくい「脳の原始的な部分」による脅迫反応です。闘争・逃走反応という自己防衛は様々な動物に見られますが、ほとんどの動物はスピーチをすることはありません。
緊張してしまうことに関する研究において、賢いパートナーがいます。チャールズ・ダーウィンは、ロンドン動物園のヘビの展示の前で 闘争・逃走反応の実験をしました。
彼の日誌には、「かつて経験したことのない危険を想像すると、私の意思や理性の力は無力であった」とあります。彼は自分の反応が現代の文明の微妙な差異に左右されない、太古からある反応であったと結論付けました。
意識のある現代の我々にとっては、スピーチがヘビにあたります。脳の他の部位はジャングルの掟にのっとって作られており、スピーチでの「へま」という「ありそうな結末」を認識するとき、命からがら逃げだすか、死を覚悟で戦うべき時なのです。
すべての脊椎動物に共通の視床下部は下垂体がACTHというホルモンを分泌するよう促し、副腎から血中にアドレナリンを放出させます。首と背中が硬直して前かがみになります。筋肉が攻撃に備えるにつれて手足が震えます。汗をかき、血圧が急上昇、筋肉や臓器へと栄養分や酸素が十分運ばれるよう、消化活動が止まって口が渇きドキドキします。瞳孔は大きく開き、近くでメモのようなものを読むのが難しくなる代わりに遠くが見やすくなります。人前であがるというのは、こういうことなのです。
では どうすればいいでしょう?
まず、見方を変えること。これは頭の中の反応ではなく、自然なホルモンによる身体反応であり、自律神経系の自動制御によるものです。社会的不安には、遺伝も大いに関係があります。
ジョン・レノンは何千回もコンサートで演奏しました。その度に、彼は緊張で吐いていたそうです。人前で何かすることを、他の人よりも恐がる人はいるものなのです。人前であがることは自然で避けられないことなので、コントロールできることに集中しましょう。
たくさん練習をすることです。ずっと前から、本番に似た環境で行いましょう。何でも練習をすることで慣れ、不安な気持ちが和らぎます。だから、いざ人前で話すときには、自分に自信を持って目の前のやるべきことをこなせるのです。
スティーヴ・ジョブズは、雄弁なスピーチを何週間も前から何百時間も練習しました。自分が言っているかが良く分かっていれば、聴衆のエネルギーを取り込めます。そうすれば、肉食動物の昼食になってしまうという「視床下部からの信号」も恐くありません。
でも、脊椎動物の視床下部は、あなたよりも何百万年も長い経験を積んでいるので要注意。舞台に上がる前こそ、ずるい手を使ってでも脳をだまさなければなりません。腕を広げて深呼吸をしましょう。これによって視床下部がリラックスするよう促します。
緊張はたいていプレゼンテーションの直前に高まるものですから、直前にストレッチをして深呼吸をしましょう。マイクへ近づくときには声ははっきりと、体はリラックスしているはずです。きちんと準備したスピーチで、あなたがカリスマ的な天才だと、荒っぽい聴衆を説得してしまいましょう。
でも どうして?
人前であがることを克服したのではなく、慣れたのです。それに実際のところ、どれほどすましていても、脳の中ではあなたもまだ野生動物なのです。物事を深く考えられ、スピーチもうまい野生動物なのです。
引用元:YouTube
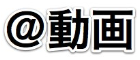
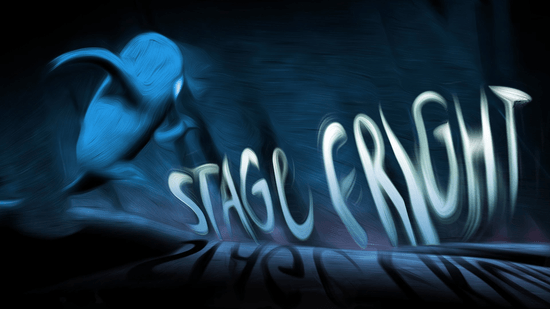


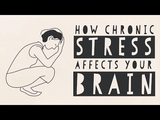 「慢性的なストレス」が脳に与える悪影響は遺伝子レベルにまで及ぶ/マデュミタ・ムルジア
「慢性的なストレス」が脳に与える悪影響は遺伝子レベルにまで及ぶ/マデュミタ・ムルジア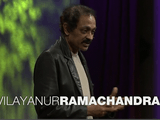 人間の顔認識システムって凄いなぁと思って調べていたら、脳の組織と心の関係についての神講演を見つけた
人間の顔認識システムって凄いなぁと思って調べていたら、脳の組織と心の関係についての神講演を見つけた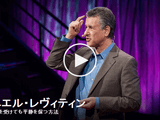 脳はストレスを受けて平静を失うとコルチゾールを放出し思考能力が低下する。ストレス下での重大な間違いを避けるためには「事前分析」が有効。/ダニエル・レヴィティン
脳はストレスを受けて平静を失うとコルチゾールを放出し思考能力が低下する。ストレス下での重大な間違いを避けるためには「事前分析」が有効。/ダニエル・レヴィティン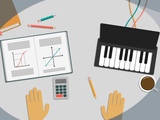 「ひと晩寝てじっくり考えよ」が正しい理由/シャイ・マルク
「ひと晩寝てじっくり考えよ」が正しい理由/シャイ・マルク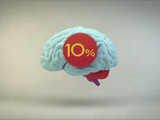 「人間は脳のたった10%しか使っていない」という神話について/リチャード・E・シトーウィック
「人間は脳のたった10%しか使っていない」という神話について/リチャード・E・シトーウィック なぜ象は決して忘れないのか?/アレックス・ジェンドラー
なぜ象は決して忘れないのか?/アレックス・ジェンドラー アルツハイマー病は正常な老化ではありません。それは治ります。/サミュエル・コーエン
アルツハイマー病は正常な老化ではありません。それは治ります。/サミュエル・コーエン 近い将来、脳に浮かんだイメージを画面に表示することが可能になるだろう/メアリー・ルー・ジェプセン
近い将来、脳に浮かんだイメージを画面に表示することが可能になるだろう/メアリー・ルー・ジェプセン あなたが恋に落ちたかどうかを知る方法/脳科学的な意味で。
あなたが恋に落ちたかどうかを知る方法/脳科学的な意味で。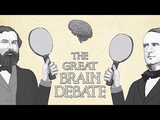 【偉大なる脳の議論】 競合的と思われた理論が、より包括的なモデルの2つの側面であったと証明されるまでの、脳科学における歴史的な紆余曲折
【偉大なる脳の議論】 競合的と思われた理論が、より包括的なモデルの2つの側面であったと証明されるまでの、脳科学における歴史的な紆余曲折 赤ちゃんが重い障害をもって生まれてきたら、親はどうあるべきなのか?/ロベルト・ダンジェロ and フランチェスカ・フェデリ
赤ちゃんが重い障害をもって生まれてきたら、親はどうあるべきなのか?/ロベルト・ダンジェロ and フランチェスカ・フェデリ 私達が甘味を好きなのは高エネルギーな糖分を好むように脳の配線が組まれた結果であり、「甘いからハチミツを好む」のではない/ダニエル・デネット
私達が甘味を好きなのは高エネルギーな糖分を好むように脳の配線が組まれた結果であり、「甘いからハチミツを好む」のではない/ダニエル・デネット 私たちの「腸」には自律した「脳」がある/Heribert Watzke
私たちの「腸」には自律した「脳」がある/Heribert Watzke より“楽観的”で、より“成功”するように脳の回路を書き換える方法/ショーン・エイカー「幸福と成功の意外な関係」
より“楽観的”で、より“成功”するように脳の回路を書き換える方法/ショーン・エイカー「幸福と成功の意外な関係」 人間の脳と行動に影響を与えている腸内に住む微生物たち/エレイン・シャオ
人間の脳と行動に影響を与えている腸内に住む微生物たち/エレイン・シャオ 脳の活動で出た老廃物(アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβなど)の除去作業は、睡眠中に行われている可能性が高い/ジェフ・イリフ
脳の活動で出た老廃物(アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβなど)の除去作業は、睡眠中に行われている可能性が高い/ジェフ・イリフ 「傷ついた脳」を修復できる日は、我々の予想よりも早くやってくる/シッダールタン・チャンドラン
「傷ついた脳」を修復できる日は、我々の予想よりも早くやってくる/シッダールタン・チャンドラン 精神的に正常であるにもかかわらず幻覚が見える「シャルル・ボネ症候群」について/オリバー・サックス
精神的に正常であるにもかかわらず幻覚が見える「シャルル・ボネ症候群」について/オリバー・サックス 人間の脳が特別になれた理由/スザーナ・エルクラーノ=アウゼル
人間の脳が特別になれた理由/スザーナ・エルクラーノ=アウゼル 「子供時代のトラウマ」が生涯に渡る健康に悪影響を与えるにも関わらず、何故これほどまでに「この問題が過小評価されている」のか?/ナディン・バーク・ハリス
「子供時代のトラウマ」が生涯に渡る健康に悪影響を与えるにも関わらず、何故これほどまでに「この問題が過小評価されている」のか?/ナディン・バーク・ハリス なぜ退役軍人は戦争が恋しくなるのか? 戦争を終わらせるには、その答えを知る必要がある/セバスチャン・ユンガー
なぜ退役軍人は戦争が恋しくなるのか? 戦争を終わらせるには、その答えを知る必要がある/セバスチャン・ユンガー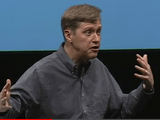 人間の脳は情報を素早く処理する装置ではなく、経験を記憶し、再生することで、常に次に起こるであろう出来事を予測する装置/ジェフ・ホーキンス
人間の脳は情報を素早く処理する装置ではなく、経験を記憶し、再生することで、常に次に起こるであろう出来事を予測する装置/ジェフ・ホーキンス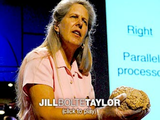 脳卒中に襲われ、自分の脳が情報処理能力を失っていくのを体験した脳科学者が、その貴重な体験から得たものとは?/Jill Bolte Taylors (ジル・ボルト・テイラー)
脳卒中に襲われ、自分の脳が情報処理能力を失っていくのを体験した脳科学者が、その貴重な体験から得たものとは?/Jill Bolte Taylors (ジル・ボルト・テイラー) 機能的MRI(fMRI)を使って「生きている」人間の脳の活動を5000人分調べてわかったこと/リード・モンタギュー
機能的MRI(fMRI)を使って「生きている」人間の脳の活動を5000人分調べてわかったこと/リード・モンタギュー 若い人たちに一言お詫びを申し上げたいと思います。/小出裕章(こいでひろあき)氏 「未来を担う子どもたちへ」
若い人たちに一言お詫びを申し上げたいと思います。/小出裕章(こいでひろあき)氏 「未来を担う子どもたちへ」 誕生日のサプライズ・プレゼントで「今からディズニーランドに行くわよ!」と言われた6歳の女の子が見せてくれた最高のリアクション
誕生日のサプライズ・プレゼントで「今からディズニーランドに行くわよ!」と言われた6歳の女の子が見せてくれた最高のリアクション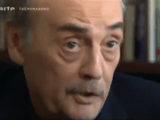 4号機が爆発した本当の原因と東電がそれを隠す理由/フランス・ドイツ共同の国営放送局 ARTE 「フクシマ-最悪事故の陰に潜む真実」(日本語字幕)
4号機が爆発した本当の原因と東電がそれを隠す理由/フランス・ドイツ共同の国営放送局 ARTE 「フクシマ-最悪事故の陰に潜む真実」(日本語字幕)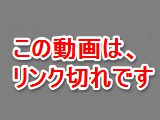 報道ステーション「イスラム国 日本人殺害予告 事件の背景には何が…」/古賀茂明さん「安倍さんの目的は人質の救出ではなく、イスラム国と戦っている有志連合の仲間に入ること」
報道ステーション「イスラム国 日本人殺害予告 事件の背景には何が…」/古賀茂明さん「安倍さんの目的は人質の救出ではなく、イスラム国と戦っている有志連合の仲間に入ること」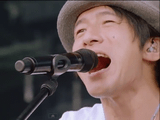 中島みゆきさんの名曲「糸」を Mr.Children の桜井和寿さんが本気でカバーしたらこうなった
中島みゆきさんの名曲「糸」を Mr.Children の桜井和寿さんが本気でカバーしたらこうなった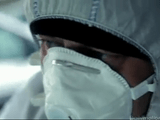 ドイツ国営テレビ放送ZDF「福島の嘘」(日本語字幕)/海外メディアが日本の癌=「原子力ムラ」を告発
ドイツ国営テレビ放送ZDF「福島の嘘」(日本語字幕)/海外メディアが日本の癌=「原子力ムラ」を告発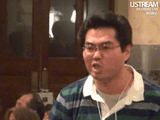 橋下さんの無責任さ、不勉強さがよくわかる・・・。ガレキ広域処理の説明会で大阪市民「モン=モジモジ氏」の全身全霊をかけた質問に一切答弁できずに逃亡する橋下市長
橋下さんの無責任さ、不勉強さがよくわかる・・・。ガレキ広域処理の説明会で大阪市民「モン=モジモジ氏」の全身全霊をかけた質問に一切答弁できずに逃亡する橋下市長 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第3集 「時代は独裁者を求めた」
NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第3集 「時代は独裁者を求めた」 消せない放射能 ~65年後の警鐘~/NNNドキュメント
消せない放射能 ~65年後の警鐘~/NNNドキュメント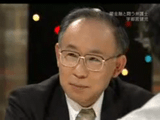 NHK・プロフェッショナル 仕事の流儀「人生も仕事もやり直せる/弁護士・宇都宮健児」
NHK・プロフェッショナル 仕事の流儀「人生も仕事もやり直せる/弁護士・宇都宮健児」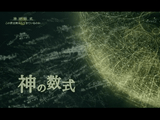 NHKスペシャル <神の数式> 第1回 「この世は何からできているのか ~天才たちの100年の苦闘~」
NHKスペシャル <神の数式> 第1回 「この世は何からできているのか ~天才たちの100年の苦闘~」 BS世界のドキュメンタリー「インサイド フクシマ」(日本語吹き替え)/BBC版に映っていた「3号機の爆発シーン」がNHK版では編集で消されている! (比較映像あり)
BS世界のドキュメンタリー「インサイド フクシマ」(日本語吹き替え)/BBC版に映っていた「3号機の爆発シーン」がNHK版では編集で消されている! (比較映像あり)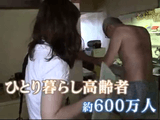 老人漂流社会 “老後破産”の現実/NHKスペシャル
老人漂流社会 “老後破産”の現実/NHKスペシャル 「だだだだだ・・・。」だけで会話を成立させる双子の赤ちゃん
「だだだだだ・・・。」だけで会話を成立させる双子の赤ちゃん 報道ステーション「国が“武器輸出”企業を支援… 低金利融資などで軍需産業化か」/古賀茂明さん「日本はアメリカのように戦争がないと生きていけない国になる」
報道ステーション「国が“武器輸出”企業を支援… 低金利融資などで軍需産業化か」/古賀茂明さん「日本はアメリカのように戦争がないと生きていけない国になる」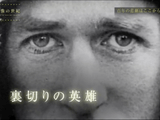 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第1集 「百年の悲劇はここから始まった」
NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第1集 「百年の悲劇はここから始まった」 化粧は詐欺だ! Bfore と After が違いすぎると話題になっていたメイク実況映像
化粧は詐欺だ! Bfore と After が違いすぎると話題になっていたメイク実況映像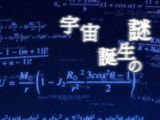 NHKスペシャル <神の数式> 第2回 「宇宙はどこから来たのか ~最後の難問に挑む天才たち~」
NHKスペシャル <神の数式> 第2回 「宇宙はどこから来たのか ~最後の難問に挑む天才たち~」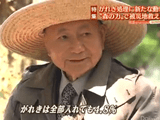 ガレキ処理に新たな動き/報道ステーションSUNDAY「震災ガレキで“森の防波堤” ~84歳学者の挑戦に密着~」
ガレキ処理に新たな動き/報道ステーションSUNDAY「震災ガレキで“森の防波堤” ~84歳学者の挑戦に密着~」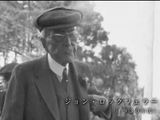 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第2集 「グレートファミリー 新たな支配者」
NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第2集 「グレートファミリー 新たな支配者」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第4集 「世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた」
NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第4集 「世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた」 被ばくした人が、どのように亡くなっていくのか?放射線が人間の臓器をどう蝕んでいくのか?/NHKスペシャル「封印された原爆報告書」
被ばくした人が、どのように亡くなっていくのか?放射線が人間の臓器をどう蝕んでいくのか?/NHKスペシャル「封印された原爆報告書」 宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【スプラッシュ祭り/ポテト】
宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【スプラッシュ祭り/ポテト】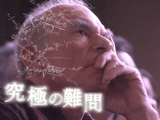 NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第3回 「宇宙はなぜ始まったのか ~残された“最後の難問”~」
NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第3回 「宇宙はなぜ始まったのか ~残された“最後の難問”~」 宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【イギリス・チーズ転がし祭り】
宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【イギリス・チーズ転がし祭り】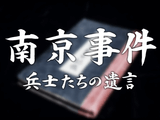 南京事件 兵士たちの遺言/NNNドキュメント
南京事件 兵士たちの遺言/NNNドキュメント 魂の反原発ソング/FRYING DUTCHMAN(フライングダッチマン)の「human ERROR(ヒューマンエラー)」
魂の反原発ソング/FRYING DUTCHMAN(フライングダッチマン)の「human ERROR(ヒューマンエラー)」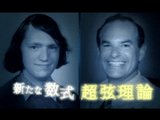 NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第4回 「異次元宇宙は存在するか ~超弦理論“革命”~」
NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第4回 「異次元宇宙は存在するか ~超弦理論“革命”~」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第5集 「若者の反乱が世界に連鎖した」
NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第5集 「若者の反乱が世界に連鎖した」